マンゴーといえば、南国のフルーツというイメージでしょう。
目をとじれば、青い空の下でまぶしい太陽を浴びた
赤いマンゴーがたわわに実っている。
あなたにもイメージできるのではないでしょうか?
今、日本に出回っているマンゴーのほとんどは沖縄で栽培されています。
マンゴーはかなりの品種があり、
実は種類が違うと味や食べ方も少し違ったりします。
マンゴーが日本に来た歴史は100年程度。
ですが、スーパーで見かけるようになったのはここ最近です。
ここであなたは疑問に思いませんか?
マンゴーが日本に来た歴史は100年ほどあるのに、
なぜ最近までスーパーに出回らなかったのでしょう。
ここでは、日本に出回っているマンゴーの種類を
歴史を追いながら、その栽培方法についてお話します。
マンゴはーどこから来たの?
マンゴーの原産地はインドです。
熱帯の果物です、ものすごく成長が早くて40メートルぐらい大きくなるそうです。
どうやって収穫するのでしょうかとおもいます。サルにとって来てもらうのでしょうか?
そんなマンゴーですが、やっかいなことに「ウルシ科」の果物です。
漆といえば、アレルギーやかぶれの原因になる代表格ですなのであわない人には
果汁でもアレルギを引き起こす可能性があるので人によっては果汁に触れるとかぶれたりします。

[ad#co-1]
マンゴーの歴史は古かった!
インド東部やミャンマーでは約4000年前から栽培が行われていたといわれているマンゴー。
なんと驚きなのは日本に登場したのは明治時代には入ってきたというこです。
見かけるようになったのはここ20年と立たないぐらいですが100年はたっていたなんて。
国内で本格的な栽培が始まったのは1970年頃だそう、当初は悪戦苦闘だったそうです。
ちょうど花粉を飛ばす時期が日本の梅雨とかぶってうまく受粉ができない状況に頭を悩ましたようです。
花粉が雨に弱いことがわかり、ハウス栽培が採用されから出回る世になりました。
あったかーい国出身なので、日本ではどうも気候があわないらしくほとんどがビニールハウス出身です。
温度管理をしっかりしないとおいしいマンゴーは実をつけてくれません。
栽培の歴史のなかに、苦労された痕跡がありますね。
日本に出回っている殆どのマンゴーが沖縄県で栽培されていますし、殆ど同じ品種です。
アップルマンゴーといわれているアーウィン種です。
スーパーでも良く見かけるやつですね。
6月からが旬の時期となりそろそろ出回るころですね。
ですがやはりお値段は高めで、まんごーはすきでもなかなか手が届きません。
日本にもいくつかの産地があり、その産地ごとで品種改良がされているのでさまざまな品種があります。
ほとんとがアーウィン種ですが、世界には他にも品種があります。
こちらの品種を見てください

キーツマンゴーといって、緑色をしていますが完熟してます。
沖縄県で栽培されていますが、赤く色づいたものが完熟しているとしか知らないと熟れてないと判断してしまいそう。
香りが強くなったら食べごろなんだとか、このキーツマンゴーは秋に出回るのだとか。
ほかにも、こちらは黄色のマンゴー

まだ許せるものですよね、ペリカンマンゴーというそうです。
ちょうどペリカンのくちばしに見えますね。
輸入されるマンゴーの代表格で、殆どがフィリピン産です。
甘みと酸味が絶妙なおいしさをだし、価格も低価格なのでファンも多いです。
日本のマンゴー栽培
日本にはかなり古くから入っているマンゴーですが、スーパーで見かけるようになったのは最近ですよね。
マンゴーの栽培方法が確立されたのが、最近になってからのようです。
沖縄では、7月ぐらいになるとホームセンターでマンゴーの苗を買うことができるそうです。
スーパーで買って食べたマンゴーのタネを、土に埋めるのでも栽培はできるようです。
しかし、マンゴーが実をつけるのは8年の歳月が必要だといわれています。
マンゴーの種タネから芽が出ても、実をつけさせるには苦労があります。
花を咲かせて受粉させないと、実がならないので花から花粉を取って受粉させないと実がなりません。
雨に弱いので、日本で栽培させて商売にすりならビニールハウスが主流のようです。
国内で生産されている90%以上はアップルマンゴーと呼ばれているアーウィン種がほとんです。
日本国内での出荷量は、3000トンに行くか行かないか程度なので希少ですね。













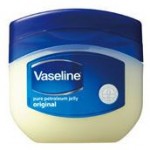




コメント